“クマ駆除ハンター”を公務員化へ 環境省が交付金で人材育成と定着支援
全国の森林や集落でクマの出没・被害が相次いでいます。こうした中、環境省は自治体が“クマ駆除ハンター”を会計年度任用職員として雇用できるよう、交付金を拡充する方針を打ち出しました。これは、専門人材を公務員として安定雇用し、育成・定着を図る新たな試みです。本記事では、この制度の狙い・仕組み・メリット・課題を、現場の声を交えながら詳しく解説します。
なぜ今、“クマ駆除ハンター”を公務員化するのか?
被害拡大と人材不足の現実
クマによる人的被害は全国で深刻化しています。2025年度はすでに死傷者数が過去最多を更新。クマが住宅地や学校近くに出没するケースも相次いでいます。
しかし、狩猟免許を持つ人材は1975年度の約52万人から、2020年度には22万人にまで減少。そのうち約6割が60歳以上という高齢化も進行中です。現場では「撃てる人がいない」「対応が追いつかない」という悲鳴が上がっています。
環境省の交付金拡充の狙い
環境省は自治体がハンターを会計年度任用職員として雇う場合に、給与・研修費用を支援する交付金制度を整備。2025年度予算要求では、従来の2億円規模から約37億円への大幅増額を検討しています。目的は「人が育たず・残らない」構造を変えること。短期委託ではなく、継続的な地域雇用として専門職を確立する狙いです。
制度の仕組み:何がどう変わる?
自治体が“専門職”として雇用
これまで多くの自治体では、駆除ハンターを臨時委託や日当制で確保してきました。その結果、ノウハウが継承されず、安定雇用が難しい課題がありました。今後は自治体がハンターを公務員として雇用し、処遇と安全を保障します。
研修・訓練の標準化
新制度では、単なる射撃技能だけでなく、生息調査・住民対応・安全管理などを含む研修体系を整備。交付金で自治体主導の研修プログラムを実施できるようにします。これにより、若手ハンターの育成・技術継承も進む見込みです。
地域定着を支援する仕組み
単年度雇用に終わらず、地域に根づく専門職をめざすため、複数年の雇用支援や住民啓発活動も交付金対象とします。これにより「ハンターが地域に定着し、住民と共に被害を減らす」という体制を目指します。
現場の声と先行事例
小諸市の「ガバメントハンター」制度
長野県小諸市は2011年から「鳥獣専門員(ガバメントハンター)」を設置し、2013年には正規公務員として採用。地域に根ざした獣害対策モデルとして全国から注目を集めています。北海道占冠村などでも同様の取り組みが進んでおり、駆除・調査・住民説明を一体化した成果が報告されています。
制度化のメリット
- 安定した雇用でノウハウが地域に蓄積される
- 安全管理や訓練制度が標準化される
- 駆除だけでなく、予防・啓発活動にも取り組める
制度化の課題
- 会計年度任用職員では長期的な安定が不十分との指摘
- 自治体による処遇格差や手当制度のばらつき
- 交付金頼みではなく、恒久的制度としての法整備が必要
政策の本質:単なる“駆除対策”ではない
この制度の本質は「地域が自らの手で自然と共生し、安全を守る」仕組みを作ることにあります。ハンターを単なる“駆除要員”ではなく、地域の安全・環境・教育・観光を支える“地域専門職”として位置づける転換点でもあります。
例えば、山間地域ではクマ対策が林業・観光・ジビエ産業とも関わります。専門人材を育てることは、地域経済や環境教育にも波及する可能性を秘めています。
今後注目すべきポイント
- 交付金の具体的配分条件や対象職種の詳細
- 自治体による採用・研修体制の実効性
- 定着支援・安全基準の標準化が実現するか
まとめと行動の呼びかけ
環境省の新制度は、クマ被害の増加という現実に対する即効的な対策でありながら、地域社会の構造改革にもつながる可能性を秘めています。人が育ち、地域に残る仕組みをどう作るか――。それが、今後のクマ対策の鍵となります。
この記事が「地域の安全」と「自然との共生」を考える一助になれば幸いです。あなたの地域では、クマとどう向き合っていますか?ぜひコメントで教えてください。そしてこの記事が役立ったと感じたら、シェアで応援をお願いします。


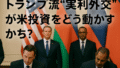
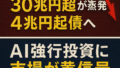
コメント