なぜ“忘れない”のか?強烈な体験を刻む脳の「選択スイッチ」──アストロサイトが記憶を操る
あなたが今でも鮮明に覚えている“あの日の出来事”、どうして忘れられないのでしょうか?
新たな脳科学研究が示すところでは、ただ神経細胞(ニューロン)だけが記憶を担っているわけではなく、意外な“脳の脇役”がその記憶を選び、強化し、定着させる「スイッチ」のような役割を果たしている可能性があるのです。
理化学研究所と九州大学の共同研究チームは、グリア細胞の一種である**アストロサイト**が強い感情を伴う体験を“選んで”記憶として定着させるメカニズムを解明しました。この記事では、その研究成果の意味と、私たちの記憶の“選択性”に迫ります。
1. 記憶は“選択されて残る”ものだった
私たちが毎日経験する数多の出来事のうち、すべてが記憶として残るわけではありません。
たとえば「今日は朝ごはんに何を食べたか」よりも、「初恋のシーン」「事故現場の一瞬」など、感情が強く揺さぶられた出来事のほうが、脳に刻まれやすいことはよく知られています。
では、その“選ばれる仕組み”とは何なのでしょうか。
これまで記憶研究では、**エングラム神経細胞**(記憶を符号化・保持する特定のニューロン集団)が注目されてきました。しかし、この神経細胞だけでは、「なぜある記憶は強く残り、他は消えるか」という問いには答えきれない面がありました。
今回の研究では、神経細胞に隠れてその“影響力”を発揮するもう一つの主役、アストロサイトがその鍵であることが示されたのです。 [oai_citation:0‡理研](https://www.riken.jp/press/2025/20251016_1/index.html?utm_source=chatgpt.com)
2. アストロサイトとは? — “のり”ではない、脳の“影の支配者”
アストロサイトは、脳内のグリア細胞の一種です。従来、グリア細胞は「神経細胞を支える脇役」的な存在と見なされてきました。しかし近年、グリア細胞が情報処理や神経活動を調節する重要な役割を持つことが明らかになってきています。
今回の研究では、アストロサイトの中で、特定のものが“強烈な体験に備える準備状態”を作り出すことがわかりました。具体的には、初回体験を契機にノルアドレナリン受容体を増やし、再体験時に応答しやすい“待機状態”になるというのです。 [oai_citation:1‡理研](https://www.riken.jp/press/2025/20251016_1/index.html?utm_source=chatgpt.com)
3. 実験で分かったこと:マウスによる恐怖条件づけ実験
・実験の流れ
研究チームはまず、マウスに“ある場所で静電気ショック”を与えることで、恐怖記憶を作らせました(初回体験)。
その後、数日後に同じ場所に戻すことで、記憶想起(=再体験)させ、脳内のアストロサイトや神経細胞の活動を観察しました。 [oai_citation:2‡理研](https://www.riken.jp/press/2025/20251016_1/index.html?utm_source=chatgpt.com)
・アストロサイト・アンサンブルの発見
再体験時にのみ活性化したアストロサイトの集団(アストロサイト・アンサンブル)が、扁桃体など複数の脳領域にわたって確認されました。
初回体験ではほとんど発火しなかったのに、想起時にだけ応答する点がこの集団の特徴です。 [oai_citation:3‡理研](https://www.riken.jp/press/2025/20251016_1/index.html?utm_source=chatgpt.com)
・ノルアドレナリン受容体の“準備スイッチ”効果
面白いことに、初回体験の後、アストロサイトはノルアドレナリン受容体(α₁およびβ₁)を数時間〜数日にかけて増やすようになります。これは、再体験時の信号を感知する“準備”とも言える変化です。
そして、この受容体量とアンサンブル活性化の強さは相関していました。 [oai_citation:4‡理研](https://www.riken.jp/press/2025/20251016_1/index.html?utm_source=chatgpt.com)
・記憶強化/抑制の操作実験
さらに、研究チームはアストロサイト・アンサンブルの働きを人工的に抑制するツール(iβARK2)を導入したところ、想起を重ねても記憶が不安定になることが確認されました。逆に、アストロサイトにβ₁受容体を強制発現させると、記憶は強く、過剰に安定化されてしまいました。 [oai_citation:5‡理研](https://www.riken.jp/press/2025/20251016_1/index.html?utm_source=chatgpt.com)
4. なぜこの発見が注目されるのか? — 忘却との闘い、記憶操作への扉
この研究成果がもたらすインパクトは大きく、いくつもの分野に波及しうる可能性を秘めています。
・“選んで残す”という概念の裏側
この発見は、脳がすべてを保存せず、あえて“必要な記憶だけを選ぶ”戦略をとる可能性を示しています。
情報過多な現代では、効率的な記憶選別機構がむしろ進化的に有利だったのかもしれません。
・学習法・記憶定着との関連
例えば「間隔を置いた反復学習(spaced learning)」が記憶に効果的とされる理由に、このアストロサイトの“準備状態”理論が通じる可能性があります。短時間に詰め込む集中学習より、適切な間隔で反復する方が、アストロサイトを“スイッチオン”させやすいかもしれません。 [oai_citation:6‡理研](https://www.riken.jp/press/2025/20251016_1/index.html?utm_source=chatgpt.com)
・精神疾患への応用(PTSD・うつなど)
強い感情を伴う記憶(トラウマ)は、PTSDやうつ、不安障害と密接に関連します。
この研究によれば、アストロサイトの働きを制御できれば、過剰に固定された記憶を和らげたり、逆に忘れられない記憶を補助的に定着させる方向性をもつ治療法が生まれる可能性があります。 [oai_citation:7‡理研](https://www.riken.jp/press/2025/20251016_1/index.html?utm_source=chatgpt.com)
5. 日常に響く示唆:私たちの“忘れない記憶”にできること
研究室でのマウス実験が、あなたの記憶をひもとくヒントをくれるかもしれません。
・感情を伴わせる「体験づくり」
単に学ぶよりも“少し強い印象を伴う経験”にすることで、脳がその記憶を選び取りやすくなる可能性があります。
例えば、ただ読書するだけでなく、感想を共有したり議論したりする行為を加えることで、“強化シグナル”を付加するようなものです。
・時間を空けて再訪する工夫
翌日・翌々日・一週間後といったタイミングで再び同じテーマや場所に“戻る”ことで、アストロサイトが“準備状態”を整えて再体験を受け止めやすくなる可能性が考えられます。
・記憶の“取捨選択”を意識する
毎日大量の情報をやり過ごしている私たちにとって、脳自身が“取る・捨てる”をしているという視点は、情報整理や記憶定着の観点からヒントになるでしょう。
本当に残したい思い出や学びには、“印象づけ”と“繰り返し”を設計的に取り入れてみてはどうでしょうか。
まとめ:記憶の“選別者”としてのアストロサイトに注目を
・強烈な体験が“忘れられない”のは、ただ神経細胞が働くだけではなく、アストロサイトが“どの記憶を残すか”を選択・安定化する“スイッチ役”を果たしている可能性が明らかになった。
・記憶想起時にのみ活性化するアストロサイト・アンサンブル、ノルアドレナリン受容体による準備状態、操作実験による記憶強化・弱化の可塑性などが、その仕組みを補強する証拠となっている。
・この発見は、記憶・学習科学、精神疾患治療、さらには私たちの日常の“忘れない記憶づくり”にまで示唆を投げかけるものだ。
もしこのテーマに興味を持たれたなら、ぜひ下のリンク先で元の研究発表を見てみてください。
さらに、あなたの“忘れられない記憶”や、“どうしてあの日を忘れられないのか”という体験談を、コメント欄でシェアしてみてくださいね。
記事が面白いと思われたら、SNSでのシェアも大歓迎です。

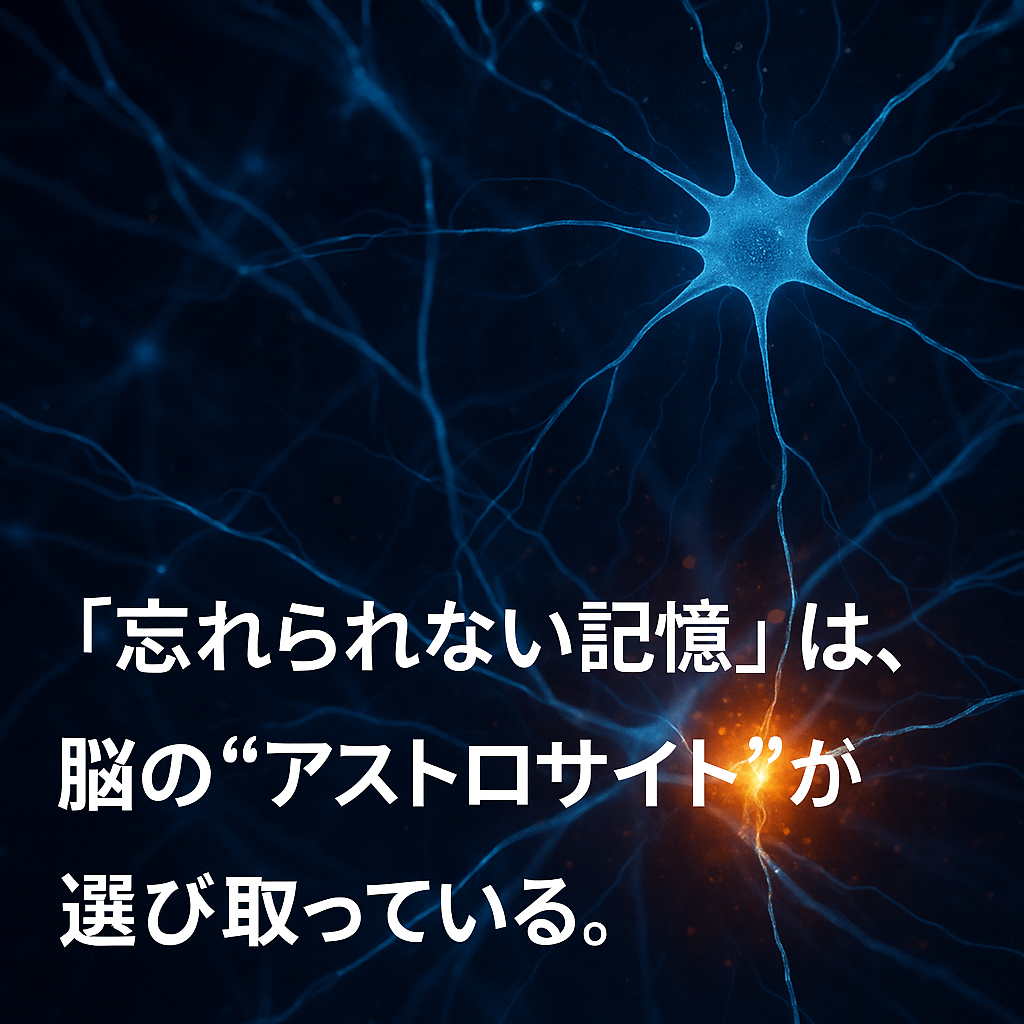
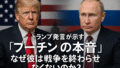
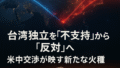
コメント