【社説解説】首相所感が問いかける「私たちの戦争」への意識とは?
「なぜあの戦争を避けることができなかったのか」──
戦後80年の節目に、ある首相が発表した所感が波紋を広げています。
過去の歴史をただ振り返るだけでなく、⼀人ひとりが自分ごととして捉えるよう促すメッセージ。その意図と限界、そして私たちにできることを、ニュースの表層を越えて丁寧に読み解きます。
1|今回の「首相所感」に込められた主張と論点
2025年10月10日、石破茂首相は記者会見で、戦後80年を迎えるにあたって所感を発表しました。 [oai_citation:0‡首相官邸ホームページ](https://www.kantei.go.jp/jp/103/statement/2025/1010kaiken.html?utm_source=chatgpt.com)
この所感では、従来の首相談話と異なり、植民地支配や侵略責任についての明言はほとんどなく、むしろ「政治制度」「議会とメディアの役割」「ポピュリズムへの警鐘」など、制度面・政治責任の視点に力点を置いています。 [oai_citation:1‡日本共産党](https://www.jcp.or.jp/akahata/aik25/2025-10-11/2025101102_03_0.html?utm_source=chatgpt.com)
特に注目すべきは、以下の3点です。
- 「無責任な人気取り政策に屈してはならない」:政治家としての良識と責任を強調 [oai_citation:2‡首相官邸ホームページ](https://www.kantei.go.jp/jp/103/statement/2025/1010kaiken.html?utm_source=chatgpt.com)
- 歴史を振り返るにあたって、政府・議会・メディアが果たすべき歯止めの重要性を指摘 [oai_citation:3‡首相官邸ホームページ](https://www.kantei.go.jp/jp/103/statement/2025/1010kaiken.html?utm_source=chatgpt.com)
- 国民自身にも「歴史を共に学ぶ責務」があるとの呼びかけ [oai_citation:4‡首相官邸ホームページ](https://www.kantei.go.jp/jp/103/statement/2025/1010kaiken.html?utm_source=chatgpt.com)
ただし、この所感は自民党内の反対意見もあり、閣議決定には至りませんでした。 [oai_citation:5‡日本共産党](https://www.jcp.or.jp/akahata/aik25/2025-10-11/2025101102_03_0.html?utm_source=chatgpt.com)
また、野党側からは「侵略責任に触れていない」「天皇制の役割を問わず」などの批判も出ています。 [oai_citation:6‡日本共産党](https://www.jcp.or.jp/akahata/aik25/2025-10-11/2025101102_04_0.html?utm_source=chatgpt.com)
すなわち、この所感は「総意」ではなく、ひとりのリーダーとしての所見と位置づけられています。
2|なぜ「自省を促す所感」が求められたのか? 背景と社会の空気
2-1 世界と日本の「平和意識」のギャップ
最新の調査によれば、現代日本人の「世界の平和」評価は平均38.3点、「日本の平和」は63.5点と、約30点近いギャップがあります。 [oai_citation:7‡q4one.co.jp](https://www.q4one.co.jp/news/20250724.html?utm_source=chatgpt.com)
また、「今後平和になる」と答えた人は日本・世界ともに約1割にとどまり、楽観的見方は少数派です。 [oai_citation:8‡q4one.co.jp](https://www.q4one.co.jp/news/20250724.html?utm_source=chatgpt.com)
一方で、「日本の平和を望む」と答えた人は94.2%に上るという調査結果もあり、強い願望とのズレが浮かび上がっています。 [oai_citation:9‡HOPIUS](https://hopius.jp/article/4212?utm_source=chatgpt.com)
このようなギャップと葛藤の中で、リーダーからの「自省」の呼びかけは、空虚な言葉にならないよう慎重さを要します。
2-2 若者と戦争記憶:接点の薄れと意識の断片化
戦後80年を目前に、若年層と戦争の記憶の距離が広がっているという指摘があります。
ある「18歳意識調査」では、17〜19歳のうち、戦争体験者から「直接話を聞いたことがある」人はわずか3割未満。 [oai_citation:10‡Nippon](https://www.nippon.com/ja/japan-data/h02497/?utm_source=chatgpt.com)
また、戦争を家族や友人と語る頻度は「ほとんどない」が7割以上。 [oai_citation:11‡Nippon](https://www.nippon.com/ja/japan-data/h02497/?utm_source=chatgpt.com)
被爆者の高齢化も進み、平均年齢は86歳を超え、今年初めて数も10万人を下回ったという報道もあります。 [oai_citation:12‡SWI swissinfo.ch](https://www.swissinfo.ch/jpn/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E9%83%BD%E5%B8%82%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%83%96/%E5%8E%9F%E7%88%86%E6%8A%95%E4%B8%8B%E3%81%8B%E3%82%8980%E5%B9%B4%E3%80%8110%E4%BB%A3%E3%81%AF%E6%A0%B8%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%82%92%E3%81%A9%E3%81%86%E8%A6%8B%E3%82%8B%EF%BC%9F/90019938?utm_source=chatgpt.com)
つまり「記憶の継承」が消えゆく中で、新たな世代が歴史とどう向き合うかは、まさにこれからの課題です。
3|所感のメッセージをどう受け止め、どう活かすか
3-1 所感の限界を見据えた読解
首相所感は、多くの政治的配慮と「言い得ぬ制約」の中で書かれているでしょう。
侵略責任に踏み込まなかった点や、天皇制についての言及がない点は、批判の的になっています。 [oai_citation:13‡日本共産党](https://www.jcp.or.jp/akahata/aik25/2025-10-11/2025101102_04_0.html?utm_source=chatgpt.com)
それでも、制度的責任への焦点、ポピュリズムへの警告、国民参加の呼びかけといったメッセージは、現代の民主主義への問いとして響いてくるものがあります。
3-2 個人にできる「自省」とは何か?
所感の呼びかけが「一人ひとりの自省」であるならば、以下のような行動を意識してみてはいかがでしょうか。
- 歴史を主体的に学ぶ: 教科書・資料館・語り部の声だけでなく、多様な視点の資料を読み、疑問を持つ
- 問いを他者と交わす: 家族・友人・SNSで戦争・平和について語り合う機会を意識的につくる
- メディアリテラシーを高める: 一面的な報道ではなく、複数ソースを比較・検証して情報を咀嚼する
- 小さなアクションから始める: 平和関連の展示・講演に足を運ぶ、署名に参加する、意見を発信してみる
「自省」は罪悪感や後ろめたさに陥るためのものではありません。
むしろ、自分の知識に限界があることを認め、問い続ける態度、自分と歴史との関係を問い直す態度こそが、未来をつくる始まりになるはずです。
まとめ:戦後80年にあって、私たちは何を受け止めるか
首相所感は、歴史的総意を示すものではなく、むしろ議論を呼び起こす起点として読むべきです。
過去の戦争をめぐって、政府・制度・個人にそれぞれ責任がありうるという視点を捉えておくこと。
そして、私たち自身が「歴史と問い続ける個人」であることが未来への種になると信じたいと思います。
この記事を読んで、あなたはどの視点に引き寄せられましたか?
コメントで

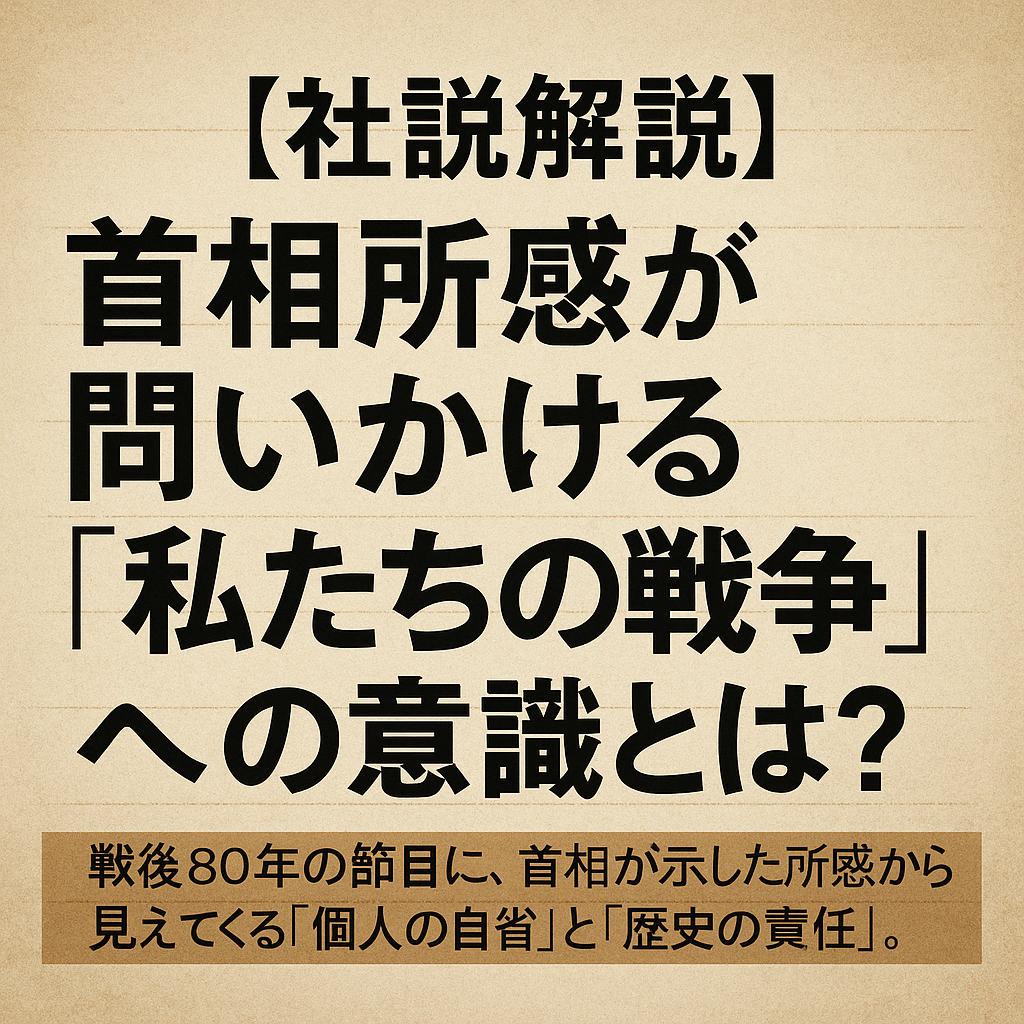
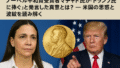
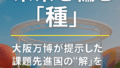
コメント