三菱商事撤退の教訓――元レノバ会長が語る「初期リスクは国が負担を」
日本を代表する総合商社・三菱商事が大型エネルギー事業から撤退――このニュースは産業界に大きな波紋を広げました。背景には、再生可能エネルギーや次世代エネルギーのプロジェクトに潜む「初期段階の巨大リスク」があります。
元レノバ会長の千本倖生氏は、「事業の初期リスクは国が負担すべき」と強調。では、なぜ商社が撤退に至り、どのような教訓を残したのでしょうか。本記事では、その背景と課題、今後の日本のエネルギー戦略に必要な視点を分かりやすく解説します。
なぜ三菱商事は撤退したのか
三菱商事はこれまで、石油・ガスを中心とした資源ビジネスから、再生可能エネルギーや水素などの脱炭素分野へシフトしてきました。しかし、今回の撤退劇は「投資額に見合わないリスク」が主因とされています。
- 規制の不透明性: 再エネ関連の政策は短期間で変化し、収益モデルが安定しづらい。
- 初期投資の巨額性: 数百億〜数千億円規模の投資が必要で、回収までに長い年月を要する。
- 技術・インフラの未成熟: 輸送・貯蔵・発電効率などが未解決の課題を抱える。
特に海外では政府が補助金や税制優遇で初期リスクを肩代わりするケースが多い一方、日本では企業が単独で背負う構造が依然として残っています。
元レノバ会長の提言――「初期リスクは国が負担を」
レノバを率いた千本倖生氏は、かつて再生可能エネルギー事業の旗振り役を務めてきました。彼が指摘するのは「官民の役割分担」の不均衡です。
「再生可能エネルギーや新技術は、最初に誰かがリスクを取らなければ始まらない。その役割を民間に押し付ければ撤退は当然。国が初期リスクを分担し、民間の成長を後押しすべきだ」
――千本倖生氏
実際、欧州では再エネ発電の「固定価格買取制度(FIT)」が普及拡大を支え、米国ではインフレ抑制法(IRA)が税控除や補助金を通じて企業の投資を後押ししています。
国際比較:日本は遅れているのか
日本の再エネ投資額は世界的に見ても低水準にとどまっています。IEA(国際エネルギー機関)の統計によれば、2024年の再エネ投資額は中国が約3,000億ドル、米国が約1,800億ドルに対し、日本はわずか200億ドル程度に過ぎません。
この差を生むのは「制度設計」です。投資初期における政府保証や税制優遇の有無が、企業のリスク許容度を大きく左右しています。国際的に見れば、日本の制度は依然として「民間依存」が強いことが浮き彫りになります。
今後の日本に必要なこと
今回の三菱商事撤退は、日本のエネルギー転換政策にとって大きな教訓です。今後必要なのは以下の3点です。
- 政府による初期リスク分担: 補助金、税制優遇、融資保証の強化。
- 官民連携の新モデル: 官が土台を整え、民が成長を担う仕組み。
- 長期的な規制安定性: 政策が変動せず、企業が安心して投資できる環境づくり。
これらが整わなければ、他の大手企業も撤退を余儀なくされ、日本の再生可能エネルギー産業は国際競争で後れを取るでしょう。
まとめ――読者への問いかけ
三菱商事の撤退は、一企業の判断にとどまらず、日本のエネルギー産業全体が直面する課題を映し出しています。初期リスクを「誰が負担するのか」という問いは、これからの政策の核心です。
あなたは、このリスクを国が担うべきだと思いますか?それとも民間が自己責任で挑むべきだと思いますか?
記事が参考になったら、ぜひコメントやシェアでご意見をお聞かせください。最新の関連ニュースもチェックしてみてください:


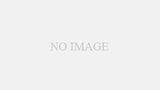
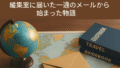
コメント