忍び寄る70年代「大インフレ」の悪夢 FRBとドルの信認危うく
世界経済に暗雲が広がっています。アメリカの物価上昇率は依然として高止まりし、
FRB(米連邦準備制度理事会)の利上げ策も十分な効果を上げられていません。
「70年代の大インフレ」の再来を想起させる声が強まっており、
ドルの信認低下や世界的な市場混乱が懸念されています。
70年代「大インフレ」とは何だったのか?
1970年代のアメリカでは、オイルショックとベトナム戦争による財政赤字が重なり、
インフレ率が年率10%を超える局面が続きました。失業率も高止まりし、
「スタグフレーション」という未曾有の経済状況に陥ったのです。
当時の教訓は、「一度インフレ心理が定着すると、金融政策だけでは制御が難しい」ということでした。
現在のインフレはなぜ収まらないのか
- エネルギー価格の不安定化:ウクライナ情勢や中東リスクで原油価格が再上昇
- サプライチェーンの分断:米中デカップリングでコスト高が常態化
- 財政赤字の拡大:コロナ後の景気刺激策で債務膨張
- 労働市場の逼迫:賃金上昇が物価高を押し上げる
これらの要因が重なり、コアインフレ率(食品・エネルギーを除く)が依然として
年率3〜4%で推移しています。
FRBの苦しい選択
FRBは2022年以降、史上最速ペースで利上げを進め、政策金利を一時5%超まで引き上げました。
しかし、インフレの根は深く、景気後退を招かずに物価を抑えるのは極めて難しい状況です。
もし追加利上げをすれば企業投資と住宅市場は冷え込み、逆に利下げすればインフレが再燃するジレンマ。
まさに「失敗すれば70年代の再現」というプレッシャーがのしかかっています。
ドルの信認は揺らぐのか
世界の基軸通貨ドルも安泰ではありません。高インフレが長引けば、
米国債の実質価値が目減りし、海外投資家がドル資産を敬遠するリスクがあります。
事実、金価格は過去最高値を更新し、中国やBRICS諸国はドル依存からの脱却を模索しています。
「ドル覇権」の揺らぎは、世界の金融秩序そのものに影響しかねません。
私たちにできる備えとは
個人レベルでも、インフレ長期化やドルの信認低下は資産運用に直結します。
- インフレに強い資産(株式、不動産、コモディティ)を一部組み入れる
- ドル一極集中を避け、通貨や地域の分散を意識する
- 短期的な金利上昇リスクを踏まえたローン・借入管理
歴史が示すのは、「インフレは気づいた時には遅い」という現実です。
今こそ早めの対策が求められています。
まとめ:70年代の悪夢を繰り返さないために
現在のアメリカ経済は、70年代の大インフレを連想させる要素を多く抱えています。
FRBは苦しい舵取りを迫られ、ドルの信認もかつてないほどの試練に直面しています。
読者のみなさんは、インフレとドルの行方についてどう考えますか?
ぜひコメントで意見を共有し、この記事をシェアして議論を広げてください。
関連リンク:
・FRB公式サイト
・国際通貨基金(IMF)
・国際決済銀行(BIS)


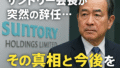
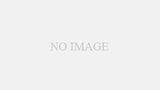
コメント