フィリピンの食文化に学ぶ市場戦略 ─ コンサルタントが掴むべき3つのインサイト
世界経済が混迷を深める中、企業は「ローカル文化から得られる学び」をますます重視しています。
特にフィリピンの食文化は、アジアの中でも独自の歴史とダイナミズムを備えており、コンサルタントがクライアントに示すべき戦略のヒントに満ちています。
米を中心とする食生活、スペインやアメリカからの外来影響、そして多様な民族背景の融合──それはまさに「グローバル市場の縮図」といえるでしょう。
本記事では、フィリピンの食文化を通して学べる市場適応力・ローカル市場理解・多様性消費の3つの視点を解説します。
コンサルタントとして、食文化を「戦略のケーススタディ」としてどう活用できるのかを探っていきましょう。
1. 「シニガン」に学ぶ市場適応力 ─ カスタマイズ戦略の本質
フィリピンを代表するスープ料理「シニガン」は、酸味のあるタマリンドをベースにしながら、地域や家庭ごとに具材が変化します。
豚肉、魚、エビ、野菜──どんな素材でも「その場にあるもの」を取り込み、バリエーションを広げていく。
この柔軟性は、まさに市場における適応力の象徴です。
実際、フィリピン発のジョリビー(Jollibee)は、この「ローカル適応」の思想を戦略に活かし、世界35か国以上に展開。
アメリカ市場では「甘いスパゲティ」や「ライス付きのセットメニュー」という現地フィリピン人向けの仕様を維持しつつ、徐々に現地消費者層にも浸透しています。
McKinseyの2024年調査によると、東南アジア市場で成功する企業の68%が「現地の食文化や習慣を商品設計に反映」していると報告されています。
コンサルタントが考えるべきは、クライアントのサービスや商品に「シニガン的な柔軟性」をどう組み込むかです。
2. 「カレンデリア」に見るローカル市場理解 ─ 価格と利便性の力学
フィリピンの街角に必ずある「カレンデリア(大衆食堂)」は、労働者や学生の日常を支える存在です。
価格は1食あたり30〜80ペソ(約80〜200円)。対してマクドナルドのセットは150〜200ペソ(約400〜530円)。
この差が示すのは単なるコスト構造ではなく、消費者が最も重視する意思決定要因です。
例えば、B2B市場においても、顧客が高価格な外資ソリューションを避け、ローカル企業の低価格・高対応力を選ぶケースが増えています。
これはまさに「カレンデリアモデル」。安価で日常的、しかも近くにある安心感が選択されるのです。
コンサルタントは価格競争に囚われるのではなく、「顧客にとっての利便性・心理的距離」をどう戦略に組み込むかを分析する必要があります。
3. 「ハロハロ」に表れる多様性消費 ─ 複合的な価値の提供
「ハロハロ」はフィリピン語で「混ぜる」を意味するスイーツ。
かき氷、アイス、ゼリー、フルーツ、豆など十数種類の素材が一つの器に盛り込まれています。
一見カオスですが、それが人々に支持されるのは「多様性を一度に楽しめる」という価値があるからです。
Kantarの2023年調査では、フィリピンのZ世代消費者の65%が「ひとつの製品に多機能性を求める」と回答。
これは「スマートフォンがカメラ・決済・SNSを兼ねる」ように、消費者が複合的な体験を期待していることを意味します。
つまり、コンサルタントが考えるべきは「単一機能で尖らせる戦略」か「多機能で囲い込む戦略」か。
ハロハロは、その判断を象徴的に示してくれます。
まとめ ─ 食文化は市場戦略の縮図
フィリピンの食文化は、単なる料理の話ではなく、ビジネス戦略に直結するヒントを与えてくれます。
- シニガン:市場適応力 ─ 柔軟にカスタマイズする発想
- カレンデリア:ローカル理解 ─ 価格と利便性の再定義
- ハロハロ:多様性消費 ─ 複合的な価値創出
コンサルタントとして重要なのは、文化を単なる表層の現象としてではなく、消費者心理と市場の構造を解き明かすレンズとして捉えることです。
次にクライアントと戦略を議論するとき、ぜひ「フィリピンの食文化」を思い出してみてください。


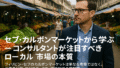

コメント