【経営課題としての“難民”】なぜ今、コンサルタントがこのテーマに注目すべきなのか?
「難民問題? それはNGOの領域でしょう?」
かつてはそう語られることが多かったかもしれません。しかし今、難民問題はESG経営、サステナビリティ、人材戦略といったテーマに直結する「経営課題」として、多くのグローバル企業に影響を及ぼし始めています。
この記事では、難民問題の現状をデータで整理しつつ、コンサルタントとしてこの課題にどう向き合い、どんな価値を提供できるのかを考えていきます。
1. 難民問題は「遠い世界の話」ではない
■ 世界で1億1,000万人以上が故郷を追われている
国連UNHCRによると、2024年末時点で世界中に1億1,000万人以上の難民・避難民が存在します。ウクライナ、アフガニスタン、ミャンマー、スーダン……国境を越えて移動する人々の流れは、戦争・気候変動・政治的迫害など、様々な要因で加速しています。
■ 企業の経済活動にも影響
たとえば欧州では、ドイツの大手自動車メーカーが難民人材を活用した人手不足解消の取り組みをスタート。日本企業でも、ローソンやユニクロなどが難民の雇用を進める動きが見られます。
「社会的インパクト × 経済合理性」を両立する打ち手として、難民雇用や支援は今後ますます注目されるでしょう。
2. 難民問題とコンサルティングの交差点
■ ESG・SDGs対応の視点から
企業がESG対応として「サプライチェーンの人権リスク」や「ダイバーシティ&インクルージョン」を重視する中で、難民支援は直接的なアクションとして評価されるようになっています。SDGsのゴール10「人や国の不平等をなくそう」にも直結します。
■ 人材不足と多様性のソリューション
少子高齢化で人材確保が課題となる日本において、難民人材は新たな労働力の源泉となりえます。実際、国内でも難民認定者の就労支援を行う企業が増え、地方の製造業や介護施設ではすでに採用実績もあります。
■ コンサルタントが提供できる価値
- 企業のESG戦略の中に難民支援を組み込む支援
- 難民雇用の制度設計・導入支援(例:多文化共生の研修設計)
- 自治体×企業×NPOの連携による共創プロジェクトの推進
これらは、単なる社会貢献ではなく、「ビジネス成果と直結するプロジェクト」としてクライアントに提示できるソリューションです。
3. 具体事例:コンサルファームによる実践
■ アクセンチュアの「難民デジタルスキル支援プログラム」
アクセンチュアはドイツや北欧で、難民に対してITスキルや言語教育を提供し、現地での就労を支援するプログラムを展開。これにより受講者の約70%が雇用に結びついています。
■ 日本における事例:PwC Japan × NPOとの連携
PwC Japanは、NPOと連携して日本に住む難民のキャリア支援に取り組み、インターンや職業訓練の場を提供。自社の人材戦略とも結びつける形で、社内の多様性推進にも波及しています。
4. 難民支援を“コンサル提案”に昇華させる視点
■ KPI設計の工夫
社会課題系の提案は、経営層への説得力がカギです。たとえば以下のようなKPIを設定することで、定量的な評価が可能になります:
- 難民人材の定着率
- ESG評価機関によるスコア改善
- ブランド認知・好感度の上昇率
■ クライアント企業のメリットを「見える化」する
CSRではなく、「成長戦略」や「リスク対応」の一部として位置づけることが、提案を通すポイントとなります。
5. まとめとアクションの提案
難民問題は、これまでの「支援対象」から、「共に社会をつくるパートナー」へと変化しています。そしてその変化は、企業の人材戦略、ESG対応、ブランディング、地域共生の観点で大きなインパクトを持ちます。
今こそ、コンサルタントとして一歩踏み出すタイミングです。
🔽 あなたにできる次の一手
- 社内のESGチームや公共セクターと連携し、「難民×ビジネス」案件を掘り起こす
- 国内外の事例を集め、提案書やピッチ資料のネタとして整理
- 実際にNPOや自治体と意見交換を行い、現場理解を深める
この記事が、あなたの次の提案テーマに少しでもヒントになれば幸いです。
▼この記事が役立ったと思ったら、ぜひシェア・コメントをお願いします。


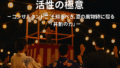

コメント