【徹底分析】オリエンタルランドが「夢の国」を超えた理由とは?〜ディズニーの裏側にある本当の戦略〜
「なぜオリエンタルランドは、年々客単価を上げながらもリピーターを失わないのか?」
コンサルタントであれば一度は考えたことがある問いかもしれません。
東京ディズニーリゾート(TDR)を運営するオリエンタルランド(OLC)は、コロナ禍を経ても売上・利益ともにV字回復。
2024年度の営業利益は過去最高の1564億円(前年比+54.7%)。
「テーマパーク事業はレガシービジネス」と言われた時代はもう終わりました。
オリエンタルランドは「夢の国」の枠を超えた戦略企業へと進化しています。
この記事では、オリエンタルランドの戦略をコンサル視点で解説。
他業界にも転用可能な示唆をお届けします。
■ なぜオリエンタルランドは「価格転嫁」に成功したのか?
「物価高でも売れる」。
2024年から2025年にかけて、TDRはパスポート価格を最大1万1900円まで引き上げました。
にもかかわらず、リピーターは減るどころか、リピーター率98%を維持(オリエンタルランドIR資料より)。
この成功の背景には、単なるブランド力ではなく、次の3つの戦略があります。
①「待ち時間」をKPIにしたUX最適化
オリエンタルランドは、待ち時間こそが最大の顧客体験リスクだと認識しています。
- 2019年:「ソアリン」導入で稼働率の平準化
- 2023年:「ディズニー・プレミアアクセス」(有料ファストパス)本格導入
- 2024年:「ファンタジースプリングス」開業で動線を再設計
結果として、顧客は「お金で時間を買う」選択肢を得た一方、
オリエンタルランドは客単価と顧客満足度の両立に成功しています。
②「オフピーク需要」の創出
オリエンタルランドは日付指定チケット制を導入し、曜日や季節による価格差を拡大しました。
これにより、従来は空いていたオフピーク時期にも来園を促進し、稼働率の平準化と単価最大化を同時に達成しています。
③「顧客囲い込み型」のホテル戦略
TDR直営ホテルの稼働率は95%超(2024年データ)。
高価格帯ホテル(東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル等)の拡充により、
ホテル予約=パークチケット購入というクロスセルモデルが完成。
「ホテル宿泊+有料プレミアアクセス」の組み合わせは、まさに顧客囲い込み戦略の教科書的事例です。
■ 「資産を持たない」フランチャイズモデルの限界を超えたOLC
オリエンタルランドは、「東京ディズニーリゾートの運営権」を持つフランチャイジーです。
一見、ディズニー社にロイヤリティを支払う受け身のモデルですが、実態は異なります。
■ 事業ポートフォリオの拡大
- テーマパーク事業:営業利益率25%超(2024年)
- ホテル事業:高収益型ストックモデルに移行
- 商業施設(イクスピアリ):収益安定化要因
- 地方創生型ホテル「千葉ディスティネーション型開発」構想(2025年発表)
OLCは「テーマパーク専業」から「体験価値創造企業」への転換を進めています。
■ 「世界で最もリピート率の高いテーマパーク」の裏側
オリエンタルランドの戦略は、単なるエンタメビジネスの枠を超えています。
たとえば、2025年には「舞浜リゾート全体を一つの都市」としてデザインする戦略を発表しました。
これは、ハーバードビジネススクールの「エコシステム戦略」に近いモデルです。
舞浜駅を起点に、ホテル、商業施設、交通、アプリ、ECまで一気通貫でUXを最適化。
「リゾートに滞在するだけで財布の紐が緩む構造」を設計しています。
■ 他業界コンサルにも役立つ3つの示唆
- 「時間価値」に課金するモデルはBtoBでも応用可能
SaaSの優先サポートやオンデマンド対応も同様のロジック。 - 「顧客との接点デザイン」が競争優位の源泉
CRMやアプリUXの設計は、今や事業戦略の中心。 - 「枠を超えた事業開発」でリスクヘッジ
本業一本足打法から、「周辺事業によるリスク分散」は多くの企業にとって参考になる。
■ まとめ|オリエンタルランドの戦略から学ぶ「体験価値経営」
オリエンタルランドは、「夢の国」の運営を超え、UXと価格戦略を高度に組み合わせた「体験価値経営」を実現しています。
「高くても行きたい」「並んでも泊まりたい」と思わせるブランドとUXの設計は、
コンサルタントにとっても強力なケーススタディ。
ぜひ、オリエンタルランドの戦略を自社案件やクライアント提案に転用してみてください。
▼この記事が役に立ったら
- コメント欄であなたの視点をぜひ教えてください。
- 同僚にもシェアして、ディスカッションを広げてください。
- 「体験価値戦略」の関連記事はこちら → 【体験価値×収益化】の成功事例まとめ

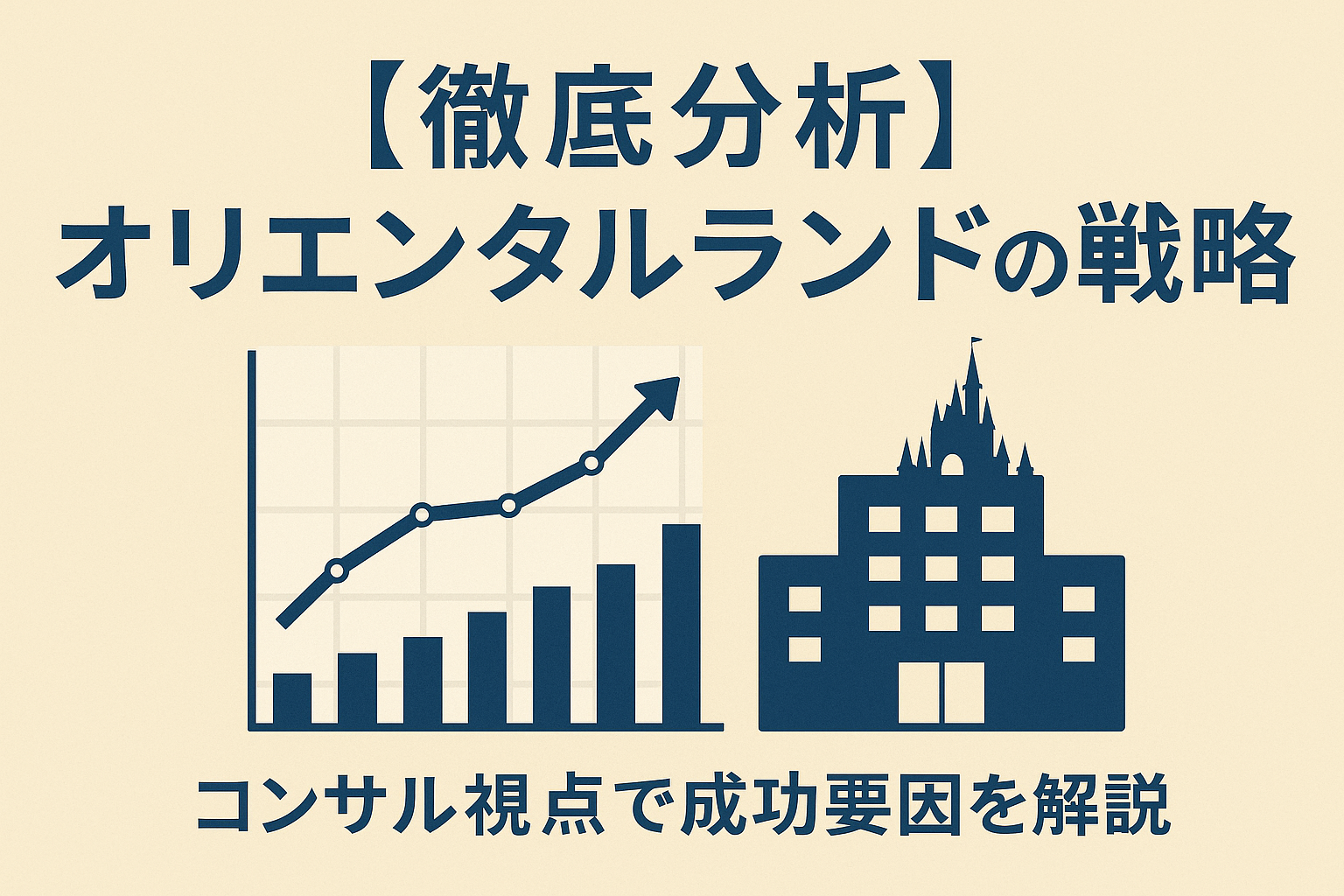


コメント