【完全ネタバレ解説】黒沢清『CURE』が怖すぎる理由|なぜ“記憶”がカギなのか?
公開日:1997年 | 監督:黒沢清 | ジャンル:サイコサスペンス/ホラー
“説明されない恐怖”がここにある──
『CURE(キュア)』は、観た人の心に長く残る、日本映画屈指のサイコスリラーです。
連続猟奇殺人事件を追う刑事と、記憶を失った謎の男。
血が飛び散るわけでも、モンスターが登場するわけでもないのに、どうしてこんなにも怖いのか?
本記事では、ネタバレを含めて『CURE』のストーリー構造、テーマ、伏線を徹底的に解説しながら、黒沢清監督の「恐怖演出の極意」に迫ります。
『CURE』のあらすじ(※ネタバレあり)
東京で次々と起こる猟奇殺人。どの事件も犯人はすぐに逮捕されるが、凶器も動機もバラバラ。
唯一の共通点は、被害者の首に“X字”の切り傷があること。
事件を追う刑事・高部(役所広司)は、ある日「自分が誰かもわからない」という謎の男・間宮(萩原聖人)と出会う。
彼は、言葉巧みに人々を催眠にかけ、無意識のうちに殺人を“引き出して”いたのだった。
なぜ人は“操られる”のか?『CURE』に潜む深層心理
● 間宮の正体:狂人か、象徴か
間宮は自分の名前も覚えていない記憶喪失者として登場しますが、実は人の心に入り込み、深層心理を刺激して“殺人衝動”を呼び起こす存在。
明確な説明はされませんが、「人の心の奥底には誰しも“殺意”がある」という前提をつきつけてきます。
● 「記憶」の消失が意味するもの
間宮も、彼に操られた加害者たちも、犯行後の記憶がない点が共通しています。
それは「自我」と「社会性」が崩壊したことの象徴であり、人間の危うさを示しているのです。
黒沢清の演出術:なぜ『CURE』は怖いのか?
● ロングショットで“恐怖の余白”を生む
この映画では、ロングショットが多用されます。観客に“何かが起こる”という不安を植えつけたまま、決定的な瞬間を見せない──
その“余白”こそが観る者の想像力をかきたて、底知れぬ不安感を与えるのです。
● 不自然な会話の間と音
登場人物同士の会話に独特の“間”があり、それが現実感を曖昧にし、どこか夢の中のような不気味さを醸し出しています。
また、静寂と生活音が交互に流れる音響設計が、観客の神経を研ぎ澄ませます。
衝撃のラストシーンの意味とは?
ラストで、高部刑事がレストランでコップを持つ店員に目を向けた瞬間、画面が静かに暗転します。
あれは彼が“間宮の役割”を引き継いだことを示唆していると解釈されています。
つまり、催眠の“感染”は終わっていない──むしろ、観客にもその暗示が向けられているのです。
『CURE』が影響を与えた作品たち
『CURE』は公開当時、国内外の映画監督に大きな影響を与えました。
クリストファー・ノーラン監督の『メメント』や、デヴィッド・フィンチャーの『セブン』との比較もよく話題になります。
どちらも「記憶」と「正体不明の犯罪者」を主軸にしており、共通するテーマ性が見てとれます。
まとめ:『CURE』は“あなた自身”を映す鏡かもしれない
『CURE』の恐怖は、誰にでもある「理性の崩壊」にあります。
それを“催眠”というフィルターを通じて見せた黒沢清監督の手腕は見事というほかありません。
あなたの中にも、まだ気づいていない「間宮」が潜んでいるかもしれません。

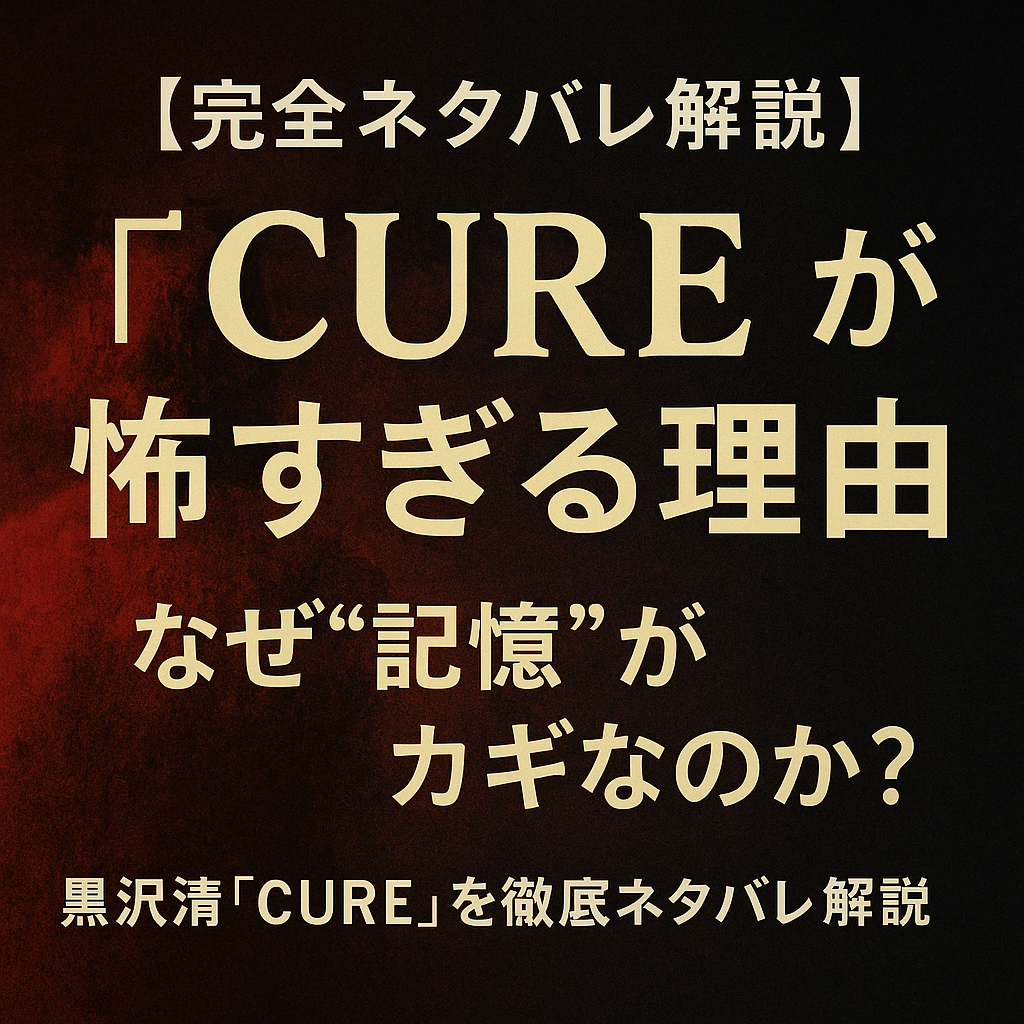
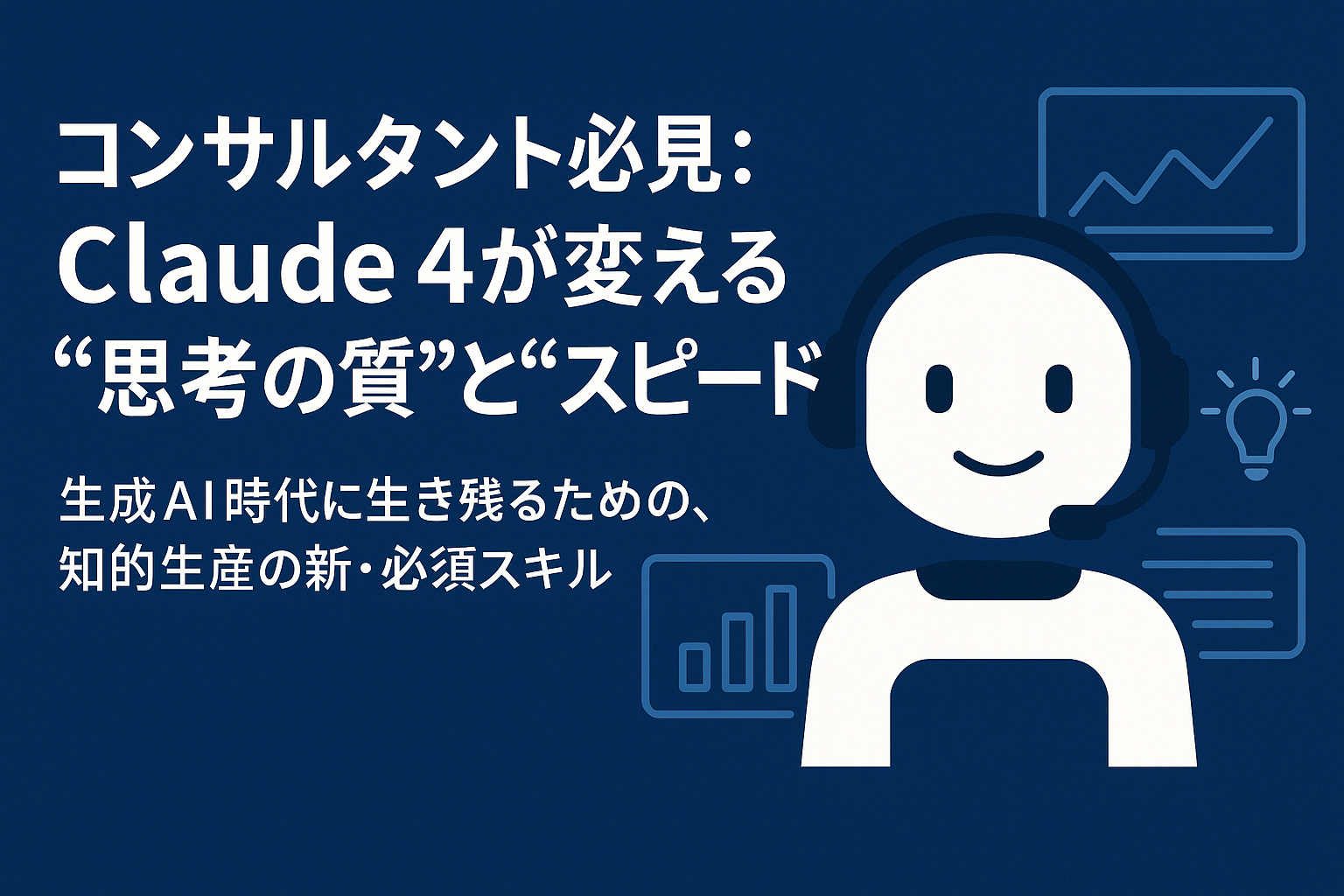
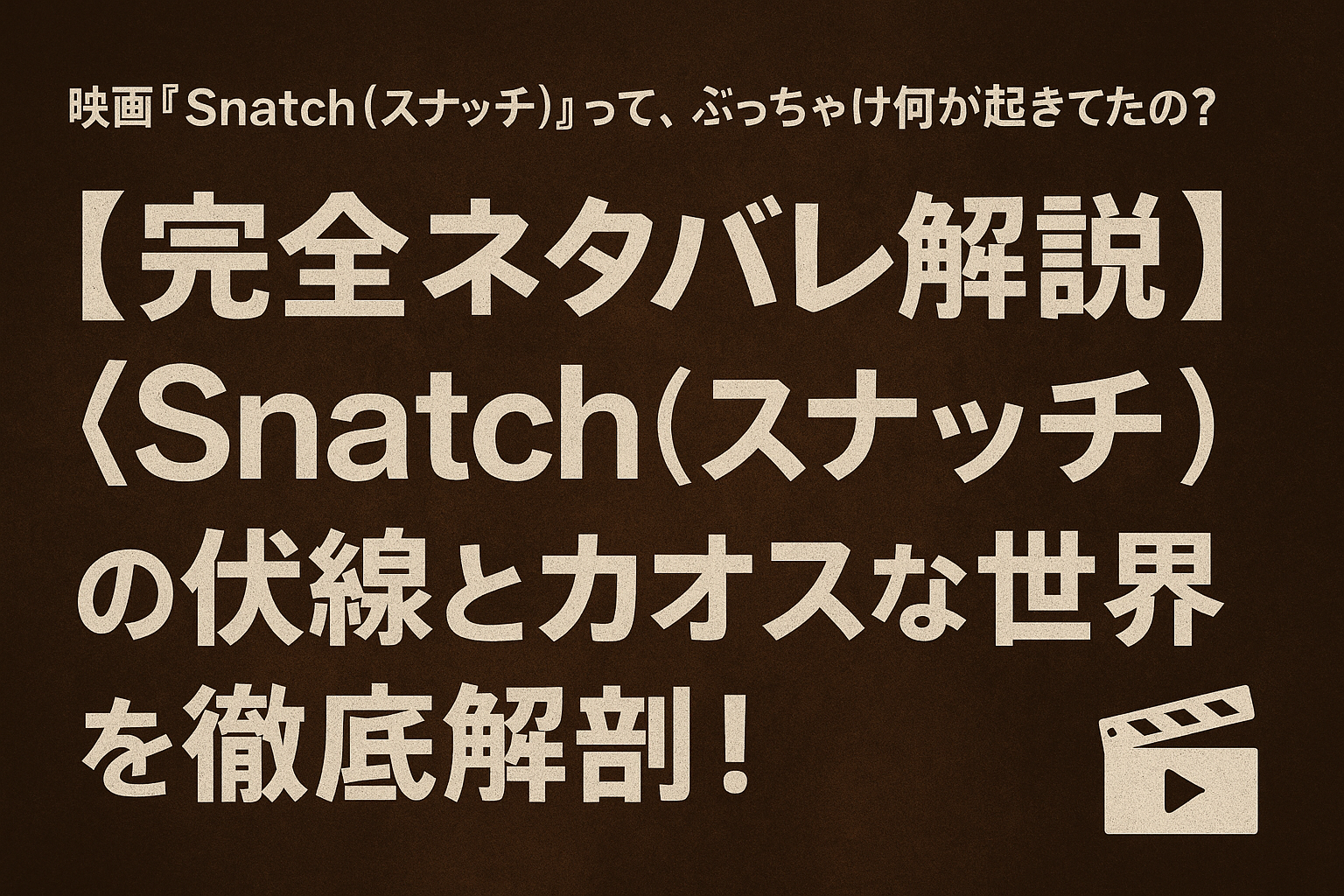
コメント