“要領の良さ”よりも“対話力”――デロイトが新卒に求める人材像とは?
「要領よく動く人が重宝される時代は終わった――」
そんな印象を抱く方も多いかもしれません。実際に、コンサルティングファーム最大手の一角、Deloitte Tohmatsu Consulting(以下:デロイト)が、新卒採用において“要領の良さ”ではなく“対話力(コミュニケーション能力)”をより重視する傾向が強まっているという報道・データがあります。本記事では、ニュースを詳しく知りたい方を対象に、「なぜ対話力が今、より重要になっているのか」「デロイトの採用プロセスではどう対話力を見極めているのか」「あなたが学生・就活生としてどう備えればいいのか」を整理してお伝えします。
① 採用市場が“要領”より“対話”にシフトしている背景
まず、“要領の良さ”とは「効率よくタスクをこなし、指示通り動ける人」というイメージが強いですが、近年の企業はこれを唯一の評価軸としていません。たとえば、2025年卒の新卒採用に関して、「コミュニケーション能力」が重視された企業は実に82.0%に上るというデータがあります。 [oai_citation:0‡jinjibu.jp](https://jinjibu.jp/article/detl/hakusho/3793/?utm_source=chatgpt.com)
一方で、「主体性」「地頭(=思考力)」といったスキルが続いており、つまり企業は“ただ素早く動く”だけでなく、“相手と対話し、課題を発掘し、調整しながら動ける”人材を求めつつあるのです。
さらに、コンサルティング業界は、クライアント企業の課題が複雑化・多様化する中で、単なる“解答を出す”作業よりも“相手(クライアントやチームメンバー)と議論しながら仮説を構築し、合意を導く”プロセスが求められています。 [oai_citation:1‡〖企業様向け〗ミイダス](https://corp.miidas.jp/assessment/6378/?utm_source=chatgpt.com)
つまり、要領の良さ=「既存の枠内で効率的に動く」、対話力=「枠を超えて関係を築き、課題を掘り起こす」という使い分けが成り立つわけです。
② デロイトが「対話力」を採用軸に据える理由
デロイトの採用プロセスを見ると、面接では行動事例・ケース問題・グループディスカッションなどの複合的な選考が用いられており、応募者の「話せる/聞ける」力が自然に問われる構造になっています。例えば、ある面接体験談には「最初に自分で考える→次に社員とディスカッション」という流れがあり、単なるプレゼン能力ではなく“雑談を交えて課題を引き出せるか”が評価されたとあります。 [oai_citation:2‡Glassdoor](https://www.glassdoor.com/Interview/Deloitte-Japan-Interview-Questions-EI_IE2763.0%2C8_IL.9%2C14_IN123.htm?utm_source=chatgpt.com)
また、採用プロセスの設計として、書類選考→オンライン適性検査→面接(行動・価値観)→ケース/ディスカッション→最終面談というステップが整備されており、いずれの段階でも“相手と意味のある対話を築いたか”が重要視される傾向にあります。 [oai_citation:3‡rocketblocks.me](https://www.rocketblocks.me/blog/deloitte-interview-process.php?utm_source=chatgpt.com)
なぜ“話せる”“聞ける”力が重視されるか。それは、コンサルタントは業務内で「クライアントの本当の意図を引き出す」「チームメンバーの異なる意見を調整する」「プレゼンを通じて関係者を巻き込む」など、“対話”の連続が日常だからです。
そのため、要領よく作業をこなすだけではなく、相手を理解し、自分の意見を伝え、共通理解を築ける能力=対話力が、プロフェッショナルとして長く活躍できる鍵になっているのです。
③ 「対話力」をどう面接で見られているのか?3つのチェックポイント
就活生・新卒対象に、対話力を面接でどう見られているかを整理します。
- 傾聴力・質問力:相手(面接官・応募者)に対して、自分だけ話すのではなく、適切な質問や確認を挟みながら会話を進められるか。 [oai_citation:4‡hrpro.co.jp](https://www.hrpro.co.jp/trend_news.php?news_no=869&utm_source=chatgpt.com)
- 説明力・構造化された発信:自分の経験や考えを、「結論→理由→具体例」という流れで分かりやすく伝えられるか。これがいわゆる“ロジカルな伝達”ですが、対話力として最低限必要です。 [oai_citation:5‡外資就活ドットコム](https://gaishishukatsu.com/archives/217611?utm_source=chatgpt.com)
- 場に応じたアジャストメント:相手・状況を踏まえて言葉遣いやトーンを変えられるか。要領よく済ませる言動ではなく、相手の反応を見ながら進められる人が評価されます。 [oai_citation:6‡sofia-inc.com](https://www.sofia-inc.com/blog/9090.html?utm_source=chatgpt.com)
面接中、「どういう経験をしましたか?」「その時どう感じました?」「その後どう動きましたか?」という問いを受けた際に、ただ時系列で話すのではなく、相手の興味を引く切り口で説明し、「面接官ってこういうこと聞きたがってるな」と即座にキャッチアップできる人が対話力ありと見なされます。
④ 学生・就活生が今すぐ取り組める“対話力アップ”の3ステップ
では、「要領よく動ける」自分から「対話できる」自分になるために、具体的にどう行動すればよいかをご紹介します。
- 日常から“相手の話を掘る”習慣をつける:例えばゼミ・アルバイト・サークルで、「相手の意図/背景」を掘る質問を一つ挟む。例えば「この活動で一番難しかったのは何ですか?その理由は?」という問いを追加すると、要領の良さだけで終わらない深みが出ます。
- 自分の経験を“対話型ストーリー”で語る:単に「私はこれをやりました」「成果は○○でした」という流れではなく、「なぜそう思ったか」「相手はどう反応していたか」「その後どう調整したか」という“相手を意識したやりとり”を意識して語ると、対話力が伝わります。
- 反応を見て軌道修正できる練習をする:模擬面接や友人との練習で「話しすぎてしまった」「相手の反応を拾えなかった」といったフィードバックを受けて、話す内容を調整する力(=聞き手との対話として進める力)を磨きましょう。
⑤ “要領”に頼りたくなる時代だからこそ気を付けたいポイント
要領よく動けることは、一見メリットに思えます。しかし、対話力がないままだと以下のようなリスクがあります。
・「与えられた仕事は速やかにこなせるが、クライアントや社内関係者との齟齬が生まれてしまう」
・「報・連・相が表面的で終わり、自分の理解とチームの理解がズレてしまう」
・「決まった枠内でしか動けず、新しい問いを発せられないため、コンサルとして成長が鈍る」
特に、コンサルティング業界・デジタル変革・グローバル案件という“不確実性の高い仕事”が増えている今、「対話して関係値を作る力」がむしろ“要領良さ”以上に評価される理由がここにあります。
まとめとアクションのご提案
本記事を振り返ると、以下のポイントが新卒採用において押さえておきたい“対話力”のキモです。
- デロイトを含む多くの企業で、新卒に「対話力(=コミュニケーション能力)」が重視されている。 [oai_citation:7‡jinjibu.jp](https://jinjibu.jp/article/detl/hakusho/3793/?utm_source=chatgpt.com)
- コンサルティング業界では、「傾聴・質問・説明・場の読み取り」といった対話力が、要領の良さ以上に成果を左右する。 [oai_citation:8‡〖企業様向け〗ミイダス](https://corp.miidas.jp/assessment/6378/?utm_source=chatgpt.com)
- 面接では“会話としての面接”であることを意識し、「相手の期待と反応を見ながら話せるかどうか」が問われる。
- 学生・就活生としては、「対話型の振り返り」「ストーリー化」「相手意識をもった練習」で対話力を鍛えられる。
では、あなたの次のステップとして以下を実践してみましょう:
- 今週1回、ゼミ・アルバイト・サークルの中で「相手に質問して対話を深めたエピソード」をメモしておきましょう。
- そのエピソードを「結論→理由→対話の流れ→結果」という構成で書き出し、1分で語れるよう練習してみましょう。
- 模擬面接か友人とのロールプレイで、“相手の反応を見て質問を返せたか”“話すだけでなく聞けたか”をフィードバックしてもらいましょう。
この記事が、「要領の良さ」一辺倒ではない、新しい就活準備のヒントになれば幸いです。読んだら、ぜひご自身の考えを書いて、“対話力をどう磨くか”をコメントでシェアしてください。そして、SNSでのシェアもぜひ。気になる方は以下の関連リンクもチェックしてみてください。
<関連リンク>

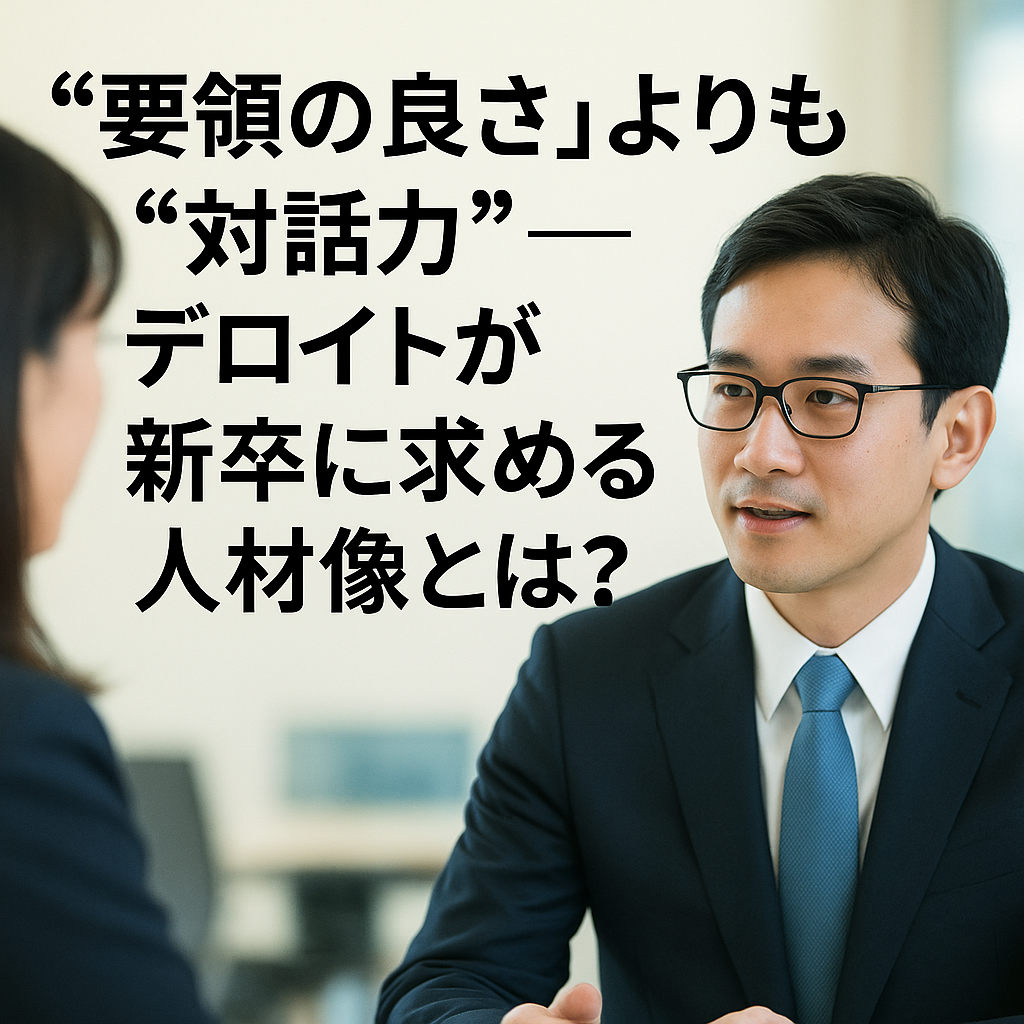
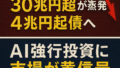
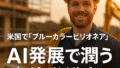
コメント