株式会社闇とは何者か?
「恐怖をビジネス化する企業」の実態とコンサル的考察
「株式会社 闇」――冗談かと思ったら、実在する。
この会社名を聞いたとき、多くの人はギョッとするはずです。
しかし、2024年に設立された株式会社闇(YAMI Inc.)は、正式に法人登記され、合法的に「恐怖」を商品化している企業です。
本記事では、コンサルタント目線で株式会社闇のビジネスモデルと成長余地、リスクについて解説します。
■ 株式会社闇とは?
「恐怖」をエンタメ化する企業
株式会社闇のミッションは、ズバリ「恐怖を届けること」。
公式サイトでは、次のように語られています。
「恐怖は、心に爪痕を残す最高のエンターテインメントです。
私たちは、都市伝説、怪談、ホラーコンテンツ、リアル体験イベントなどを通じ、
“恐怖を楽しむ場”をプロデュースしています。」
主要事業
| 事業名 | 内容 |
|---|---|
| 闇プロデュース | 廃墟体験、心霊スポットツアー、恐怖イベントの企画・運営 |
| ホラーコンテンツ制作 | 動画、書籍、ゲーム、都市伝説コンテンツの制作 |
| 広告・PR支援 | ホラー系PRイベントのプロデュース(例:映画・ドラマタイアップ) |
まさに「恐怖を売る会社」と言えるでしょう。
■ 収益モデルはどうなっているのか?
① BtoC:恐怖体験イベントで収益化
「闇プロデュース」のイベントは、若年層に人気です。
特にZ世代は「非日常体験」をSNSでシェアする傾向が強く、ホラー系コンテンツと相性が良い。
2024年夏イベント「都市伝説ナイト」では、1万人超を動員。
チケット単価:5,000円~10,000円
グッズ販売比率:約30%(ホラーTシャツ・御札・限定動画)
② BtoB:ホラータイアップのPR支援
最近はBtoB事業も拡大しています。
- ホラー映画の公開PRイベント
- ゲーム会社の恐怖体験キャンペーン企画
- メタバースホラー空間の共同制作
イベントプロデュース料:500万円~3,000万円(案件規模による)
③ メディアコンテンツ
「闇チャンネル」というYouTubeホラーコンテンツも展開。
チャンネル登録者数:2025年7月時点で約12万人。
動画広告収益+企業案件(再生単価は一般のエンタメ動画より高め)
■ コンサル目線で考える「株式会社闇」の可能性とリスク
【メリット】社会的ニーズにフィットした市場
・Z世代の「エンタメ疲れ」に刺さるホラーコンテンツ
・リアル体験×デジタル拡散(UGC化)との相性◎
・イベント+物販+コンテンツ多面的マネタイズ
市場規模(参考):
ホラーイベント市場 約150億円(2024年)
ホラー映画市場 約200億円
都市伝説コンテンツ市場(Web・出版・配信)約50億円
【リスク】炎上と法規制リスク
- 過激な演出による事故リスク(例:心臓疾患誘発、転倒)
- コンテンツの信憑性問題(都市伝説の捏造→炎上リスク)
- 自治体や宗教団体からのクレームリスク(心霊スポット利用など)
特に「心霊体験」や「恐怖体験」は、事故やクレームのリスクを常に抱えています。
コンサルタントとしては、リスク管理と法務体制の構築支援が重要です。
■ コンサルが関与する余地は?
① 事業戦略
- 恐怖エンタメ×メタバース(VRホラー体験の開発)
- 海外展開(アジア圏ホラーフェスへの進出)
- IP化(キャラクター・ストーリーの多展開)
② リスクマネジメント
- 演出ガイドラインの策定
- 危機管理マニュアル作成(炎上対応・事故対応)
- 法務チェックフローの構築(薬機法・景表法リスク回避)
③ データ活用とLTV設計
- イベント来場者データ×EC販売への誘導
- ファンコミュニティ運営によるリテンション設計
- ホラーデータの分析による新規コンテンツ提案
■ まとめ:恐怖ビジネスは「闇」か「光」か?
株式会社闇は、単なるホラー会社ではありません。
恐怖をエンターテインメントとして昇華し、ビジネスモデルを確立しつつあります。
ただし、過激化すれば「社会問題化」「炎上」のリスクも。
コンサルタントとしては、
- 市場拡大の可能性
- リスクマネジメント
- 倫理と収益のバランス
この3点を意識して関与することが求められます。
▼ 行動喚起
この記事が参考になった方は、ぜひシェアしてください。
「恐怖マーケティング×ビジネス戦略」の事例集も無料配布中。
こちらからダウンロード

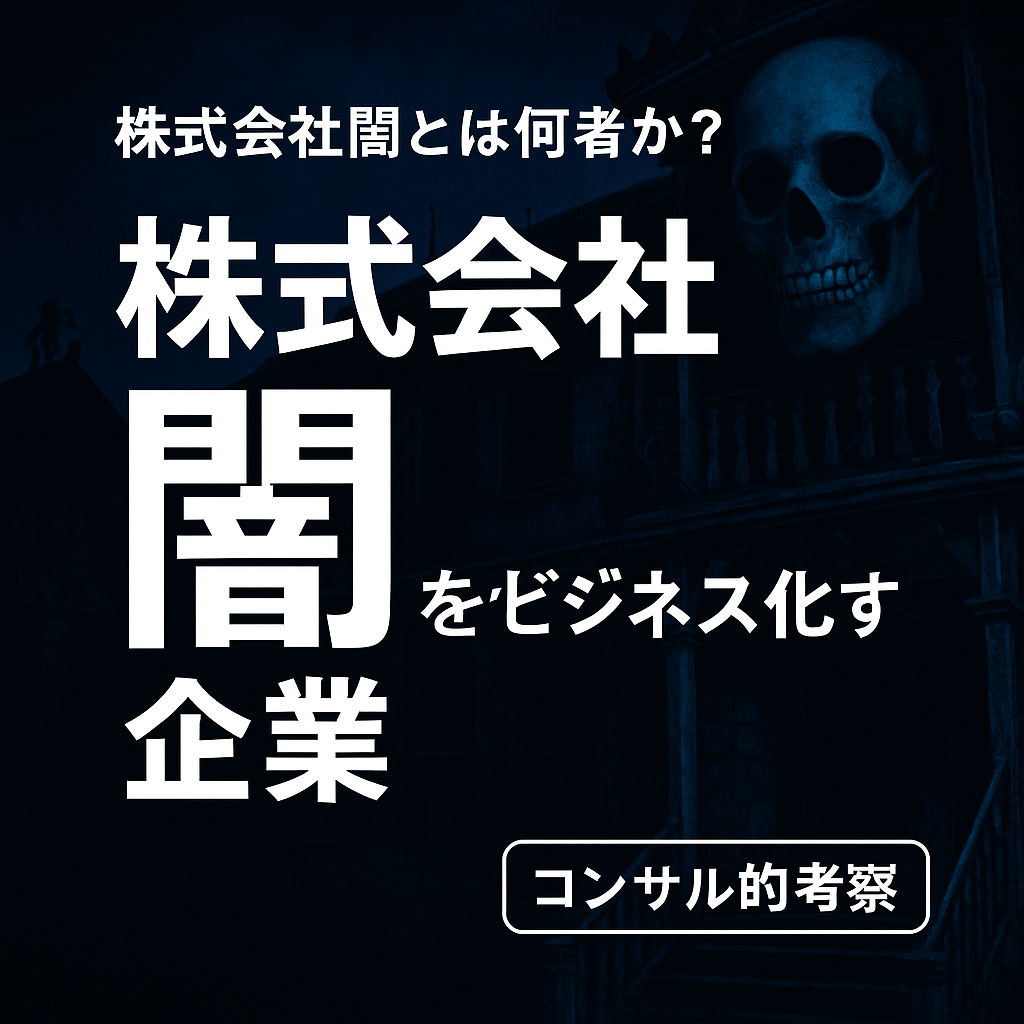
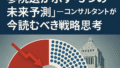
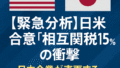
コメント