売上があっても利益が出ない理由とは?
経営者のための「利益率」改善ガイド
「売上は上がってるのに、なぜか手元にお金が残らない……」
そう感じたことがある経営者の方、多いのではないでしょうか?
売上が伸びているのに利益が出ない。その原因は、単なる支出の増加ではなく、「利益率」というシンプルかつ強力な指標を見逃しているからかもしれません。
本記事では、経営者が知っておくべき「利益率」の本質と、すぐに実践できる改善策を、具体的な事例とともにわかりやすく解説します。
利益率とは?売上だけでは見えてこない真実
「利益率」とは、売上に対してどれだけ利益が出ているかを示す指標です。
一般的には以下のように計算されます。
利益率(%)=(利益 ÷ 売上)× 100
例えば、月商1,000万円で利益が100万円なら、利益率は10%です。
売上が高くても利益率が低ければ、ビジネスとしては不健全。逆に、売上が控えめでも高い利益率を維持していれば、安定した経営が可能です。
利益率が低い企業の共通点
- 価格競争に巻き込まれている
- 業務効率が悪く、人件費やコストがかさんでいる
- 原価や固定費の見直しをしていない
- 高単価の商品やサービスが不足している
たとえば、ある製造業の中小企業では、営業チームが売上拡大に奔走していたにもかかわらず、実際には粗利益率が年々下がっていました。調査の結果、安売りキャンペーンが原因で粗利が削られていたことが判明しました。
経営者が押さえるべき3つの利益率改善アクション
1. 利益率の見える化と定期チェック
まずは、自社の各事業・商品ごとの利益率をしっかり可視化しましょう。月次で利益率の推移を確認することで、「稼げていない商品」や「利益を圧迫しているコスト」が明らかになります。
2. 高利益率商品への注力
利益率の高い商品やサービスに経営資源を集中させるのは、非常に効果的です。たとえば、あるIT系ベンチャーでは、受託開発よりも自社SaaSプロダクトの方が利益率が2倍以上高かったため、方針を転換し黒字転換を果たしました。
3. 原価と間接費の見直し
無駄なコストを削減することも利益率改善には欠かせません。サブスクリプションの整理、仕入先の見直し、業務のアウトソーシングなど、固定費や変動費を「利益率」の視点で見直してみましょう。
データで見る:利益率の高い企業の特徴
2024年の中小企業白書によると、黒字企業の平均営業利益率は8.3%。一方で、赤字企業の平均はわずか2.1%に留まります。
利益率が5%を超えるかどうかが、安定経営のボーダーラインとも言えるでしょう。
業種にもよりますが、以下は一例です:
| 業種 | 平均営業利益率 |
|---|---|
| 小売業 | 3.5% |
| 製造業 | 6.8% |
| IT・情報通信 | 12.4% |
同業他社と比較し、自社のポジションを見直すことも、戦略立案の重要なヒントになります。
まとめ:売上よりも「利益率」に目を向けよう
- 売上が上がっても利益が出なければ意味がない
- 利益率は経営の健全性を示す重要な指標
- 定期的な可視化と分析、コストの見直し、戦略転換が鍵
今こそ、「売上」ではなく「利益率」に目を向けるタイミングです。
自社の利益構造を見直し、持続可能な成長を実現しましょう。
この記事が参考になった方は、ぜひSNSでのシェアや、コメント欄でのご意見・ご質問をお待ちしています!

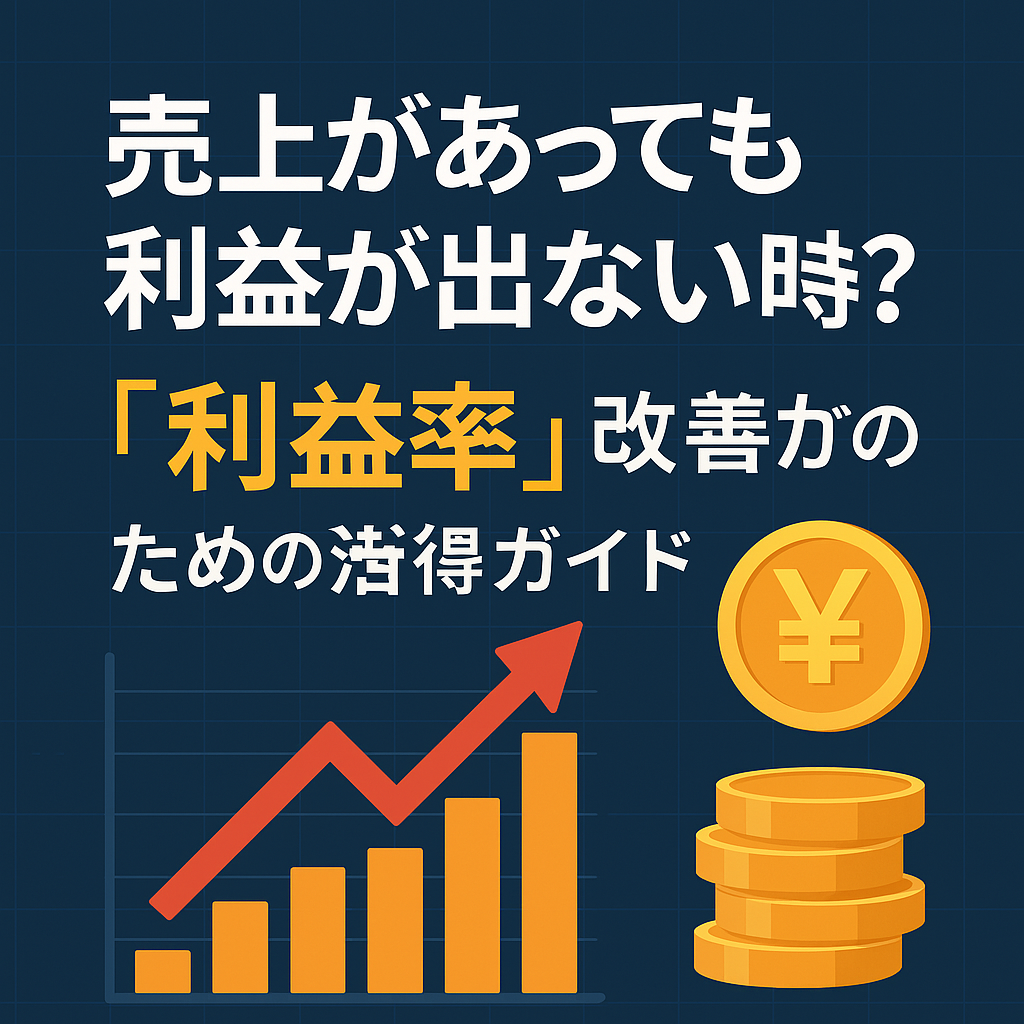


コメント