『哀れなるものたち』を語り尽くす:現代映画における「再生」と「逸脱」の傑作
映画評論家必見! ヨルゴス・ランティモス監督の新境地にして、エマ・ストーンのキャリアを塗り替える衝撃作『哀れなるものたち』。本稿では、その映像美と倫理観の越境を、評論家の目線から徹底的に掘り下げる。
リード:ジャンルの「解体」か、それとも「再構築」か?
2023年のヴェネチア国際映画祭で金獅子賞を受賞した『哀れなるものたち(Poor Things)』。観客の多くは、エマ・ストーン演じるベラ・バクスターの奇怪な人生に目を奪われながらも、作品の根底に潜む「問い」に気づく。「人間とは何か」「女性の自由とはどこまで許されるのか」。本作は単なる風刺でもない、SFでもない、フェミニズム映画とも言い切れない、まさにジャンルの再構築を試みる試金石だ。
ヨルゴス・ランティモスと「逸脱」の美学
『ロブスター』『聖なる鹿』からの進化
ランティモス監督の作品群には一貫して「逸脱」というテーマがある。『ロブスター』(2015年)では社会制度の不条理を風刺し、『聖なる鹿の殺害』(2017年)では古典悲劇の様式を現代に再構築した。
今作『哀れなるものたち』では、その逸脱がより快楽的かつヴィジュアル的に描かれており、「醜さ」と「美」の境界を崩壊させている。
「本作では、生きるという行為そのものが美的実験として提示されている」 — 『カイエ・デュ・シネマ』評論より
エマ・ストーンが体現する「再生の肉体」
ベラ・バクスターは、自殺した女性の身体に赤ん坊の脳を移植するという衝撃の設定で蘇る。いわばフランケンシュタイン的存在でありながら、その成長は人間以上に人間的だ。
エマ・ストーンはこの役で、第81回ゴールデングローブ賞主演女優賞を受賞し、さらにオスカーの最有力候補とも目されている。
特筆すべきは、ベラの身体性が「男性の欲望の対象」としてではなく、「自らの快楽と好奇心の道具」として描かれている点。これは従来のフェミニズム映画とは異なる、ラディカルでポストヒューマン的な視点を提示している。
美術と撮影:19世紀の夢と悪夢のあいだで
本作の美術監督はジェームズ・プライス(『女王陛下のお気に入り』)が務め、撮影はロビー・ライアン(『ロブスター』)が担当。ヴィクトリア朝の建築、オリエンタリズム、スチームパンク、アール・ヌーヴォーが混在する世界は、まさに「哀れなるものたち」の精神構造の投影だ。

批評家として注目すべき3つの視点
- フェミニズムのアップデート:自由とは「自分の欲望に忠実であること」だとする大胆な再定義。
- ジャンルの再構成:SF、ゴシック、風刺、寓話が交錯するポストモダン的語り口。
- 倫理のグレーゾーン:人間改造、死の乗り越えといったタブーへの踏み込み。
まとめ:映画評論家に問われる想像力の再訓練
『哀れなるものたち』は、観客の「見方」を根底から揺さぶる。フェミニズム映画として、ポストヒューマン作品として、あるいは風刺喜劇として、本作はどこから切っても批評の余地がある。
しかし、それらを束ねるのはやはり「逸脱」することへの賛歌であり、「再生することの痛みと希望」なのだ。
映画評論家に求められるのは、この混沌を恐れず、むしろ歓迎する想像力である。本作をどう捉えるかは、あなた自身の「見る力」が試されているとも言えるだろう。



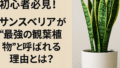
コメント